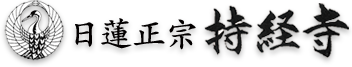総本山第六十七世日顕上人猊下御指南
十三、妙法の三世の功徳
末法の我々は機根が下(くだ)っているため、自分白身の前世のことは暗昧(あんまい)である。しかし、仏法の三世の因果より見れば、すべての衆生が、前世より善悪の種々の業を作っている。よく見れば、人々の過去の因縁がどうであったかは、現在の結果を正しく見れば、そこにおのずから明らかに出ているのであり、未来の結果がどうなるかは、現在の因縁を見れば、また明らかである。今世に妙法に巡り値(あ)い、題目を唱える人は、前世に大きな仏縁の功徳を積んでいる故に、妙法を聞いて信を起こすのである。
(総本山第六十七世日顕上人猊下御教示『すべては唱題から』 18ページ)
特設ページ
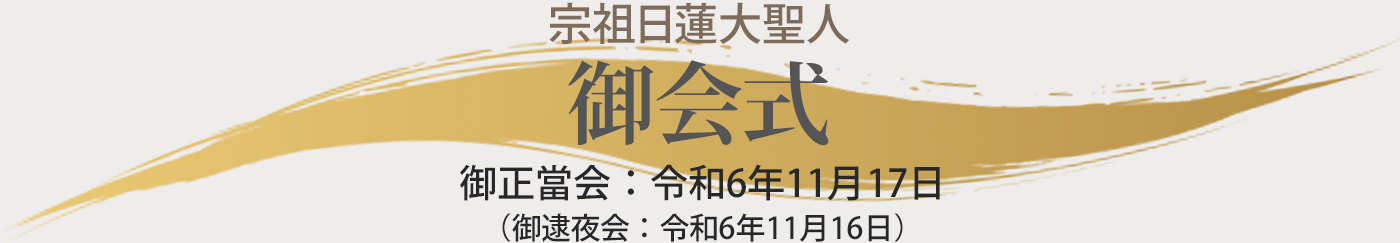
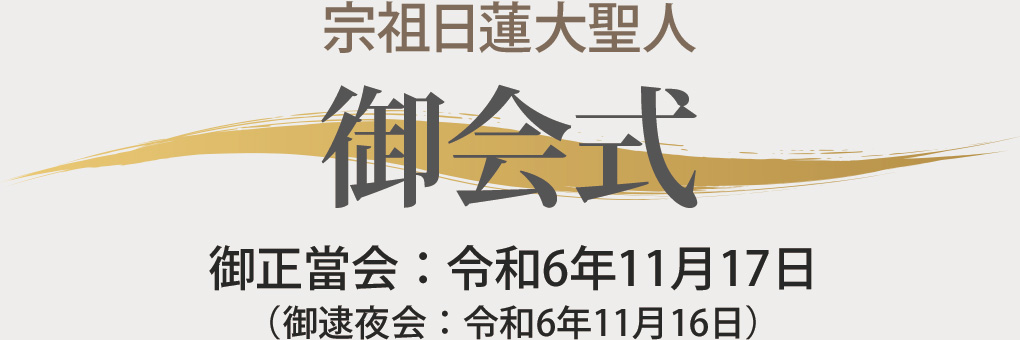

令和6年11月17日(日)午後2時より、持経寺本堂において当山「宗祖日蓮大聖人・御会式(おえしき)御正當会(ごしょうとうえ)」が厳粛に奉修されました。
御会式とは、末法の御本仏・日蓮大聖人が弘安5年(1282年)年10月13日、武州池上(現在の東京都大田区)の右衛門太夫宗仲の館において御入滅あそばされ、滅・不滅、三世常住(さんぜじょうじゅう)の相を示されたことをお祝いする法要です。
» 続きを読む




特設ページ一覧
【令和4年から】★成人式
【令和7年】★本堂大改修工事【令和6年】★御会式(11月17日)★お餅つき(12月15日)【令和5年】★御会式(10月15日)★宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年慶祝記念 支部総登山(4月・9月・11月)★お餅つき(12月17日)【令和4年】★御会式(10月23日)★お餅つき(12月18日)【令和3年】★大乗山持経寺 座替り式 並 第三代住職入院式(11月26日)★お餅つき(12月19日)
令和7年8月
■お経日(1日) ■広布唱題会(3日) ■御報恩御講(10日) ■盂蘭盆会(15日)
盂蘭盆会(15日)

令和7年8月15日、午前10時と午後1時の2回にわたり、盂蘭盆会が持経寺本堂において奉修されました(写真はすべて午後1時の部)。
法要は読経・焼香・唱題、各家塔婆供養等の追善回向と如法に厳修され、そののち天野御住職より目連(もくれん)尊者と盂蘭盆会の起源について、「目連尊者は幼くして死別した母・青提女(しょうだいにょ)を神通力をもって探したところ、欲深く、物を惜しんだ慳貪(けんどん)の罪によって餓鬼界に堕ちていた。悲しんだ目連尊者は神通力によって食べ物を母に与えたところそれが炎となり、それを消そうとしてさらに炎は大きく燃え盛り母を火だるまにし苦しめ、自身の小乗教の神通力では母を救えなかった。これは、私たちが父母のため先祖ためどんなに立派な孝養の志を立てても、供養の方法を誤り、その教えが無力であれば、自己満足にはなってもその小善は大悪となり、逆に父母を苦しめる結果となることを意味する。そこで目連尊者は釈尊に教えを乞い、7月15日に百味の飲食を添え十方の聖僧を招いて供養し、母を餓鬼道の苦しみから救うことができたが、しかしそれはわずか一劫の間、餓鬼道の苦悩から救ったに過ぎず、母を成仏させることはできなかった。そののち、目連尊者はこれまでの小乗教や方便の大乗教を捨て、釈尊の出世の本懐(ほんがい)である法華経を受持信行し成仏の記別を受け、その法華経の功徳により母も父も成仏することができたのである。」等と述べられ、さらに『盂蘭盆御書』の御文を引用され、「末法の時代に生きる私たちは、真に父母を救いその成仏を願うならば、まず自身が南無妙法蓮華経のお題目をしっかり唱えて成仏得道を目指すことが大切である。本日こうしてお塔婆を建立し、僧俗一致して読経・唱題・焼香した皆さんは、これ以上ない大善業の姿である。今後ともお盆やお彼岸に限らず、折りあるごとに寺院に参詣してお塔婆を建立し、僧俗一致して御回向申し上げましょう。」等との御指導をいただきました。
『盂蘭盆御書(うらぼんごしょ)』
弘安2年7月13日 58歳
目連(もくれん)が色心は父母の遺体なり、目連が色心、仏になりしかば父母の身も又仏になりぬ。
(御書1376頁)



御報恩御講(10日)

令和7年8月10日午後1時より、御報恩御講が持経寺本堂において奉修されました。
法要は献膳・読経・唱題と如法に厳修され、天野御住職より令和7年8月度・御報恩御講拝読御書『弥源太殿御返事』を拝読申し上げ、御法話に先立ち種々御挨拶をいただいたのち、拝読御書の通解並びに御述作当時の背景および同抄全体の概要等について述べられ、「〈通塞(つうそく)の案内者〉との大聖人様の仰せは、末法の一切衆生を成仏に導く大導師であるとの御教示であり、私たちは大聖人様の正法を堅く受時信行申し上げ、自身の成仏得道に向かって信心第一に精進することが大切である。」等と述べられ、さらに総本山第六十七世日顕上人様の御指南を引用され、「自身における閉塞した道を開くために、しっかりとお題目を唱えていくならば、必ずその先の光が見えてくる。私たちの人生は山あり谷ありで、平坦な人生が有り難いと思っていてもそうはいかないのが娑婆世界である。道が塞がれたときに、今こそお題目を唱えるときなのだと自覚できるかどうかが、その困難を乗り越えられるかどうかの分かれ道になる。大変な問題に正面からぶつかって乗り越えていく、開かれていくための力は唱題行しかない。」等との御指導をいただきました。
また御報恩御講終了後、各総地区ごとに集まって折伏誓願達成に向けてのミニ座談会が開催されました。
『弥源太殿御返事(やげんたどのごへんじ)』
文永11年2月21日 53歳
南無妙法蓮華経は死出(しで)の山にてはつえ(杖)はしら(柱)となり給(たま)へ。釈迦仏(しゃかぶつ)・多宝仏(たほうぶつ)・上行(じょうぎょう)等の四菩薩(しぼさつ)は手を取り給ふべし。日蓮さきに立ち候(そうら)はゞ御迎(おんむか)へにまいり候(そうろう)事もやあらんずらん。又さきに行かせ給はゞ、日蓮必ず閻魔法王(えんまほうおう)にも委(くわ)しく申すべく候。此(こ)の事少(すこ)しもそら(虚)事あるべからず。日蓮法華経の文(もん)の如くならば通塞(つうそく/仏道の妨げを取り除く)の案内者なり。只(ただ)一心(いっしん)に信心おはして霊山(りょうぜん)を期(ご)し給へ。
(御書722頁16行目〜723頁3行目)




広布唱題会(3日)

令和7年8月3日午前9時より、広布唱題会が持経寺本堂において奉修されました。
読経・広布唱題行終了後、天野御住職より種々ご挨拶をいただき、そののち御指導に先立ち『持妙法華問答抄』を拝読申し上げ、「名聞(世間一般での地位・名声・名誉)名利(財産・お金への執着)、我慢(慢心・増上慢)偏執(自分の誤った考えに偏った姿)によって大聖人様の仏法を信ぜず蔑ろにすることは恥ずべき恐ろしいことであり、成仏も叶わない。しかし我慢偏執はいけないけれども、信心根本の正しい姿の中において名聞名利を追い求めることは決して間違いではない。山のような金銀財宝があったとしても使い方を誤ってしまっては無駄になるが、しっかり御本尊様を拝する正しい姿の中においては、御供養を含め金銀財宝も正しく活かされるようになる。どこまでも本門戒壇の大御本尊を中心に、御法主上人猊下の御指南のままに、自行と化他行の折伏によって自身と周りの方々の幸せのために精進してまいりましょう。」等との御指導をいただきました。
『持妙法華問答抄(じみょうほっけもんどうしょう)』
弘長3年 42歳
名聞名利(みょうもんみょうり)は今生(こんじょう)のかざり、我慢偏執(がまんへんしゅう)は後生(ごしょう)のほだし(紲/足かせ)なり。嗚呼(ああ)、恥(は)づべし恥づべし、恐るべし恐るべし。
(御書296頁2行目〜3行目)


お経日(1日)

令和7年8月1日、午前10時より、お経日が持経寺本堂において奉修されました。
法要は読経・唱題、各家塔婆供養・永代供養精霊等の追善回向と如法に厳修され、そののち御法話に先立ち、天野御住職より『減劫御書』を拝読申し上げ、通解並びに本抄全体の概要等について述べられたのち、さらに『観心本尊抄』『諸経と法華経と難易の事』の御文を引用され、「私たちは〈世間法即仏法〉たることを理解しなければならない。一般の方々は、仏法と世法の道理が分からない。皆、誤った宗教によって人生が曲がり苦しんでいくのである。今こそ私たちは正しい大聖人様の仏法をもって折伏を行じ、迷い苦しむ人々を一人でも多く救っていかなければならない。大聖人様の弟子檀那として、地涌の菩薩の眷属として、しっかりと折伏行に励んでまいりましょう」等との御指導をいただきました。
『減劫御書(げんこうごしょ)』
建治元年 54歳
法華経に云(い)はく「皆(みな)実相と相(あ)ひ違背せず」等云云。天台之(これ)を承(う)けて云はく「一切世間の治生産業(じしょうさんごう)は皆実相と相ひ違背せず」等云云。智者とは世間の法より外(ほか)に仏法を行なはず、世間の治世(じせ)の法を能(よ)く能く心へて候を智者とは申すなり。
(御書925頁13行目〜15行目)
『如来滅後五五百歳始観心本尊抄(にょらいめつごごごひゃくさいにはじむかんじんのほんぞんしょう)』
文永10年4月25日 52歳
天晴れぬれば地(ち)明らかなり、法華を識(し)る者は世法を得(う)べきか。
(御書662頁1行目)
『諸経と法華経と難易の事』
弘安3年5月26日 59歳
仏法は体(たい)のごとし、世間はかげのごとし。体曲がれば影なゝめなり。
(御書御書1469頁9行目〜10行目)



令和7年7月
■お経日(1日) ■広布唱題会(6日) ■御報恩御講(13日)
■お知らせ
令和7年7月15日、午前10時および午後1時の2回にわたり、盂蘭盆会が持経寺本堂において奉修されましたが、ホームページ編集室の都合により、今回は掲載をお休みさせていただきます。読者の皆さまには何とぞご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
御報恩御講(13日)

令和7年7月13日午後1時より、御報恩御講が持経寺本堂において奉修されました。
法要は献膳・読経・唱題と如法に厳修され、天野御住職より令和7年7月度・御報恩御講拝読御書『一生成仏抄』を拝読申し上げ、御法話に先立ち明年の持経寺創立60周年および特別御供養について種々御指導ののち、拝読御書の通解並びに、宗旨建立よりおよそ2年後に御著述あそばされた同抄全体の要旨等について述べられ、「私たちの、煩悩にとらわれて曇った生命の鏡は、お題目を受持信行する功徳によって磨かれ、何があろうと左右されない堅固な仏様の悟りのお姿になる。そして自行化他であるから、自身の鏡を磨くと同時に、折伏して他の人々の鏡をも磨いていかなければならない。」等と述べられ、さらに御法主日如上人猊下の御指南を引用され、「折伏は大変であるし、相手が受けてくれるかどうかは別問題であるけれども、しっかりと慈悲の心をもって、大聖人様の仏法、御本尊様の大事をお伝えしていくことが大切である。決して諦めることなく、たとえ一言二言でも折伏していくことで智慧が湧いてくる。これからも自身と他の人々の幸せのため、唱題をかさね折伏行に精進してまいりましょう。」等との御指導をいただきました。
また御報恩御講終了後、各総地区ごとに集まって折伏誓願達成に向けてのミニ座談会が開催されました。
『一生成仏抄(いっしょうじょうぶつしょう)』
建長7年 34歳
只今(ただいま)も一念無明(いちねんむみょう)の迷心(めいしん)は磨(みが)かざる鏡(かがみ)なり。是(これ)を磨かば必(かなら)ず法性真如(ほっしょうしんにょ)の明鏡(みょうきょう)と成るべし。深く信心を発(お)こして、日夜朝暮(にちやちょうぼ)に又(また)懈(おこた)らず磨くべし。何様(いかよう)にしてか磨くべき、只(ただ)南無妙法蓮華経と唱(とな)へたてまつるを、是をみがくとは云(い)ふなり。
(御書46頁16行目〜18行目)
御法主日如上人猊下御指南
したがって折伏に当たっては、まず、しっかり唱題に励むことが肝要であります。御本尊様に祈り、相手を思う一念と強い確信が命の底から涌き上がってきた時、その確信に満ちた言葉は、必ず相手の心を揺さぶらずにはおかないのであります。
すなわち折伏は、相手の幸せを祈り、不幸の根源である邪義邪宗の謗法を破折し、この妙法を至心に信じていけば、必ず幸せになれることを誠心誠意、伝えていくことが大事なのであります。
(『大日蓮』令和7年6月号)



広布唱題会(6日)

令和7年7月6日午前9時より、広布唱題会が持経寺本堂において奉修されました。
読経・広布唱題行終了後、御指導に先立ち、天野御住職より『開目抄』を拝読申し上げ、「私たちは火に焼かれる鉄のように、折伏を行ずることで鍛えられる。そして折伏は、急流に木を入れて漕ぎ大波が立とうと、また眠っている師子を起こして吼えられようと、力強い覚悟と慈悲をもって臨まなければならない。それがなければ、折伏のその一言が出てこない。その根本となるのは唱題の功徳である。」等と述べられ、さらに「常に前進しようという強い思いがあれば、御本尊様はそれを必ず享受させてくださる。必ず成就できるとの確信がなければ、信心している意味がない。強い気持ちを持って、家庭のこと、折伏のこと、お寺のことを常に御本尊様にご祈念し前進してまいりましょう。」等との御指導をいただきました。
『開目抄(かいもくしょう)下』
文永9年2月 51歳
鉄(くろがね)は火に値(あ)はざれば黒し、火と合ひぬれば赤し。木をもって急流をかけば、波、山のごとし。睡(ねむ)れる師子に手をつくれば大いに吼(ほ)ゆ。
(御書573頁7行目〜8行目)


お経日(1日)

令和7年7月1日、午前10時より、お経日が持経寺本堂において奉修されました。
法要は読経・7月唱題行、各家塔婆供養・永代供養精霊等の追善回向と如法に厳修され、そののち御法話に先立ち、天野御住職より『白米一俵御書』を拝読申し上げ、通解並びに本抄の概要等について述べられたのち、「〈事供養/じくよう〉とは、仏様に、財宝等への執着を破すために財宝を供養し、そして一番大切な命を御供養することであり、〈理供養/りくよう〉とは、欲深い慳貪(けんどん/物惜しみをすること、貪欲なこと)の心を破すために信心の真心を仏様に差し上げることである。私たち末法の凡夫は自身の命、体を差し上げることはできないけれども、御本尊様を固く信じて自身の命に代わる財宝等を御供養することで〈帰命〉に通じ、その姿によって成仏得道を遂げていくのである。」等と述べられたのち、第六十七世日顕上人様の御指南を引用され、「このくらいの信心、このくらいの折伏で良いだろうとか、自分勝手な考えでは十四誹謗の姿となる。それぞれの思いはあっても、その自我を乗り越えて、これからも御本尊様のために自行化他の信心修行に精進してまいりましょう」等との御指導をいただきました。
『白米一俵御書(はくまいいっぴょうごしょ)』
弘安3年 59歳
南無と申すはいかなる事ぞと申すに、南無と申すは天竺(てんじく)のことばにて候。漢土(かんど)・日本には帰命(きみょう)と申す。帰命と申すは我が命を仏に奉ると申す事なり。我が身には分に随(したが)ひて妻子・眷属(けんぞく)・所領・金銀等もてる人々もあり、また財(たから)なき人々もあり。財あるも財なきも命(いのち)と申す財にすぎて候(そうろう)財は候はず。さればいにしへ(古)の聖人(しょうにん)賢人(けんじん)と申すは、命を仏にまいらせて仏にはなり候なり。
(御書1544頁7行目〜11行目)
総本山第六十七世日顕上人御指南
この南無(帰命)ということには「没我(もつが)」という意味が含まれています。つまり、命を帰(き)すという意味は、信仰の対象に対し、自分自身の我(が)を没するということであります。したがって、自分自身の我が強く、正直で素直になれない人間は、心からの帰命ということができません。
(『妙法七字拝仰上巻(大日蓮出版発行)』より)



CONTENTS

〒211-0025
川崎市中原区木月3-35-12
電話:044(411)6826
■過去のトップページ一覧
◎令和3年12月 ◎令和4年1月 ◎令和4年2月 ◎令和4年3月 ◎令和4年4月 ◎令和4年5月 ◎令和4年6月 ◎令和4年7月 ◎令和4年8月 ◎令和4年9月 ◎令和4年10月 ◎令和4年11月 ◎令和5年1月 ◎令和5年2月 ◎令和5年3月 ◎令和5年4月 ◎令和5年5月 ◎令和5年6月 ◎令和5年7月 ◎令和5年8月 ◎令和5年9月 ◎令和5年10月 ◎令和5年11月 ◎令和5年12月 ◎令和6年1月 ◎令和6年2月 ◎令和6年3月 ◎令和6年4月 ◎令和6年5月 ◎令和6年7月 ◎令和6年8月 ◎令和6年9月 ◎令和6年10月 ◎令和6年11月 ◎令和6年12月 ◎令和7年1月 ◎令和7年2月 ◎令和7年3月 ◎令和7年4月 ◎令和7年5月 ◎令和7年6月 ◎令和7年7月